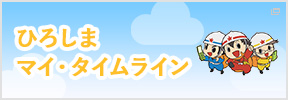活動報告 REPORT
令和6年度予算特別委員会において母子生活支援施設について質問いたしました。
(以下、一部抜粋)
――――――――――――――――――
こどもまんなか社会の実現を目指し、社会全体で子供の成長を後押しするためのこども家庭庁が昨年4月に創設されました。子供の貧困、孤立、家庭内DV、児童虐待など、今も厳しい環境に取り残されている子供の存在を忘れてはいけません。
最悪の事態から命を救うことさえできれば、児童相談所の一時保護の後、子供は社会的養育を受けながら生きていくことができます。私はこれまで、児童相談所の拡充や里親の推進、里親のフォスタリング事業、ファミリーホームの充実など、社会的支援が必要な子供の養育について議会で質問をし、施策の充実を訴えてきました。
このたびは、同じく社会的養育の施策の一つである母子生活支援施設について質問をさせていただきます。
Q. 【石田】
まず、母子生活支援施設とはどのような施設で、どのような役割を果たしているのでしょうか。
A.こども・家庭支援課長
母子生活支援施設は、児童福祉法第23条及び第38条に基づき、配偶者のない母、またはこれに準ずる事情にある母の申込みにより、母とその者が監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立の促進のために、その生活を支援することを目的とする児童福祉施設です。施設においては、入所者の自立の促進を図るため、単に住む場所を提供するだけでなく、入所に至った経緯や生活困難な状況などの個々の事情に寄り添い、生活基盤の安定や健康の維持、養育支援や親子関係の調整、子供の成長・発達を支援していきます。入所世帯は、独立した居室で生活するとともに、家事等の習得や就労に向けた支援、子育て相談、子供の学習等の支援を受け、自立を目指しています。
Q. 【石田】
母子生活支援施設は広島県に何施設あり、そのうち広島市には何施設で、場所はどこにあるのでしょうか、また、広島市の施設への入居状況について教えてください。
A.こども・家庭支援課長
母子生活支援施設は広島県内に9施設あり、そのうち広島市には南区の宇品東と段原山崎の2施設、西区草津東に1施設、安佐北区亀山に1施設、合計4施設があります。
令和6年2月1日現在での本市の4施設の入所状況は、4施設の定員が合計で90世帯のところ、45世帯の入所となっています。
Q. 【石田】
母子生活支援施設措置費等支弁の令和6年度予算額は幾らでしょうか。
A.こども・家庭支援課長
令和6年度予算額は2億2645万9000円です。
なお、この予算額には、DV被害等を理由として県外・市外の施設に入所する世帯分の措置費等も含みます。
Q. 【石田】
母子生活支援施設の入所要件や入所までの手続の流れはどうなっていますか。
A.こども・家庭支援課長
入所の対象となるのは、配偶者のない母、またはこれに準ずる母であって、監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合であり、具体的には、母子家庭は母が生計の中心となって児童の養育の責任を果たさなければならないのですが、生活、住宅、教育、就職等の解決困難ないろいろな問題を抱えていることにより、監護すべき児童の心身に好ましくない影響を与え、母が児童の監護の責任を十分果たし得ない場合などです。
入所までの手続の流れですが、まず、各区福祉課において入所を希望する理由や生活状況等の聞き取りを行い、入所要件を満たしているかなどの確認を行います。入所要件をおおむね満たしている場合は、施設見学をしていただき、本人が各区福祉課への入所申込みを行います。入所申込みと同時に健康診断を受診し、伝染性疾患のおそれがないことを確認の上、施設入所となります。
Q. 【石田】
行政の担当者に紹介されない限り、この母子生活支援施設の存在を知ることはほとんどありません。施設を紹介するか否かは、相談を受けている行政の担当者が判断するわけですけれども、その行政側の基準と施設が考えている基準とに隔たりがあるように感じます。
そこで、お伺いします。区の福祉課へ相談があっても、入所に至らないのは、どのような理由でしょうか。
A.こども・家庭支援課長
各区福祉課では、独り親家庭の様々な相談を受けており、母子生活支援施設への入所も含め、各家庭の状況に応じて、子供のために一番よい支援方法を検討しています。入所相談があった場合には、生活状況を聞き取るとともに、施設の概要等を説明しているところですが、ペットを飼育している、子供を転校させたくないなどの理由により入所を断念したケースや、施設に門限や来客の制限がある環境に抵抗感があることで入所に至らない場合などがあります。そのほか、転居先として適当な場所が見つけられず、一時的なアパート代わりとして利用したいなどの入所要件を満たさない場合もあります。
Q. 【石田】
支援が必要な家庭が母子生活支援施設につながればと思いますが、どのように取組をされているのでしょうか。
A.こども・家庭支援課長
特に困難を抱える世帯は、周囲が気づき、支援につないでいくことが重要であるため、日頃から様々な相談を受けている各区厚生部の地域支えあい課や生活課に母子生活支援施設のよさを周知するとともに、要保護児童対策地域協議会を構成する幅広い関係機関にも周知し、施設での支援が有効と考えられる方に積極的に案内してもらうよう依頼しています。
【石田】
相談者の生活状況を聞き取る各区の福祉課の方をはじめ、母子家庭と関わりのある皆さんがこの施設の役割を十分に理解した上で、必要な方には施設入所を案内して、1組でも多くの母子がこの施設で生活を立て直し、前向きに生きていけることを期待いたします。
(令和6年度予算特別委員会②へ続く)